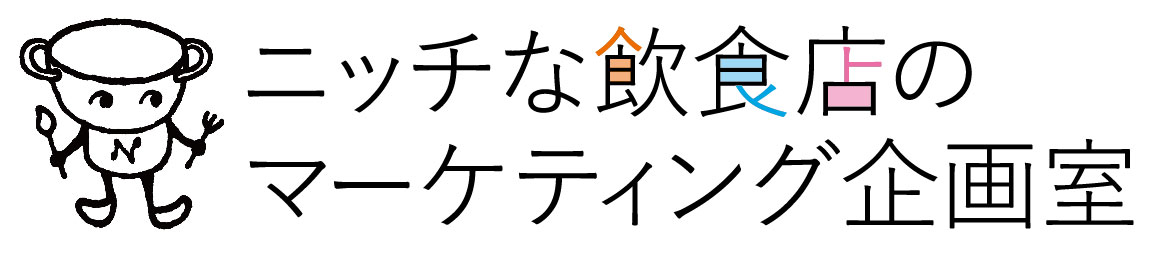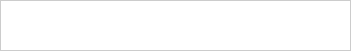ここでは8つのカテゴリーのうち地域ニッチ飲食店の事例についてレポートします。カテゴリーの区分けは別ページを参照してください。またこのカテゴリーの市場と顧客分析は予測概論を参照してください。
●高田馬場のミャンマー料理店が人気
高田馬場駅の周辺にミャンマー料理店が20店ほど集まっています(2021年時点)。都内では、ここ以外のミャンマー料理店は数店舗です。ほんとんどのミャンマー料理店がここに集まっていることになります。
高田馬場周辺に集まったのは1990年ごろから。ミャンマーの政治的混乱、技能実習生・留学生制度などによってミャンマー人が増加したからです。さらに近くにミャンマー人僧侶のいるお寺があったこともあるようです。異国の地、日本で暮らすためには同郷の仲間が近くにいることや心の支えがある方が安心できますね。
●集まることによる効果。認知度向上とPR効果
高田馬場は「リトルヤンゴン」とも呼ばれています。地下鉄東京メトロのCMで高田馬場のミャンマー料理店が紹介されたことがありました。石原さとみさんが民族衣装のようなファッションとへアスタイルで登場。メッセージは「高田馬場で、アジアの深みにハマっちゃいました。」
テレビ、交通広告でのPRによる集客効果の大きさは計り知れないものがあります。おそらく数億円規模の広告予算が使われたものと思います。ひとつの店舗ではとてもできるものではありません。たくさんの店舗が集中したことで広告に取り上げられました。
店舗が集まることの効果はそれだけではありません。近くに同じミャンマー料理店があれば必然的に「ちょっと変えたい」という気持ちが高まります。ましてや多民族のお国がらです。少数民族のモン族、シャン族の店もあります。ミャンマー家庭料理の店、ヌードル専門の店などそれぞれに特徴を出そうとしています。
それぞれが差別化をすると「今度はあの店に行ってみたい」と一度では終わりません。地域への再訪率が高まります。地域全体としてリピートしてもらえることは、結果として再来店と同じです。店舗の売上増加には再来店してくれるお客さまが最重要です。
●店舗が集まることでニッチが構築される
ニッチは選ぶだけではニッチになりません。ニッチというポジションをつくりあげていくことが必要です。生態学で言う「ニッチ構築」です。詳しくは別ページをご覧ください。
ニッチが構築できれば、それはビジネス用語で言う「参入障壁」になります。参入障壁とは、新しい競争相手が入ってくること防ぐことを言います。
高田馬場のようにミャンマー料理店が集中すると、ほかの飲食店がここで多店舗を展開することはできなくなります。「リトルヤンゴン」という名前がついて有名になっている以上、ラーメンでもイタリアンでも、高田馬場を別の飲食店の名所にすることは困難になります。競争する相手は入ってこれない、つまり壁ができたということです。
このように店が集積されるケースを「ドミナント型のニッチな飲食店」と命名してみました。わかりやすいのは月島の「もんじゃストリート」。100店ちかくの店が集まっています。テレビなどで取材されることの多さ、ほかの地域で対抗することの難しさなど圧倒的なパワーになってお客さまが集まっています。
ドミナント(dominant)とは本来、支配的なという意味です。しかしここでは集積と考えます。コンビニのセブン‐イレブンが日本でビジネスをはじめたときにドミナント戦略を使って展開しました。一定の地域に集中的に出店して効率をあげる方式です。
店の認知度が高まる、商品の配送がしやすい、店をサポートする本部スタッフも動きやすいなど効率がいい戦略として有名になりました。
高田馬場のミャンマー料理店もセブン‐イレブンほどの現代的な戦略とはいえませんが、結果的にはドミナント戦略になり、少なからず成功を納めています。
●ドミナント型のニッチな飲食店の3つの成功戦略
ドミナント型のニッチな飲食店。では、どうしたらうまくいくのかをまとめてみました。
①集まる店舗が都心であること
ニッチな飲食店では「商圏(どこからお客さまがくるか)」を広く考える必要があります。ニッチなので近くにたくさんのお客さまがいません。お客さまの層は薄く限られています。したがって高田馬場のような人が集まりやすい都心であることが必要になります。
②それぞれが個性的であること
認知度やPR効果を考えると、同じようなタイプではなく、それぞれの店がすこしずつ変わってることが必要です。これによって「またここに来たい」となります。ミャンマー料理店では少数民族の店があるなど個性的です。各店の個性が重要です。
③近隣との協力があること
ミャンマー料理店が高田馬場に集まったのは必要があったからです。法律や社会的ルールなど堅苦しい日本のなかで生きていく、ビジネスしていくためには互いに協力し、助けあうことが必要だと思います。仲の良い集団の形成は成功のための必須要件に思えます。
「仲良きことは美しき哉」。武者小路実篤を思い出しました。
<参考文献>
室橋裕和『日本の異国: 在日外国人の知られざる日常』晶文社 2019年

※このページは2018年10月17日のブログを改稿して作成しています