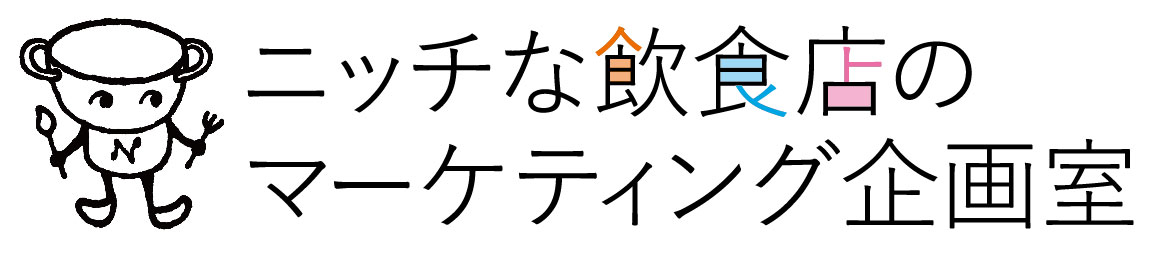仰々しいタイトルにしてみました。以前、チャーハン巡礼記を書いて、自分が!面白かったので続編です。
今回は「日本のチャーハンはこうあるべきだ」という試論つきです。つまるところ、日本の米と魚と発酵食品でつくるべきだということです。「タイトルの割には大したことない。前回同様、ただのチャーハンの食べ歩きだ」と言われるかもしれません。
原稿用紙20枚分の長編です。チャーハン好きの人にはおすすめです。「結論はなに?早くしろよ」という、それほどチャーハンが好きでない方は下記の「チャーハン巡礼記。およその内容」をご覧ください。
●チャーハン巡礼記。およその内容-ここさえ読めば十分
前回は同僚とともにチャーハンの名店を巡りました。そこからインド料理のビリヤニにたどりつきました。これが想像以上においしくチャーハンの将来性について思いを馳せたところで終了となりました。
今回はもう少し深く掘っています。と言っても原稿の多くは親切な同僚が作成したチャーハンに関する研究をちゃっかり借用させてもらっています。親切な人に感謝です。
1.米とチャーハンは中国が起源
稲作は約7000年前の揚子江下流からはじまった。チャーハンは隋(581~619)の時代の「碎金飯(さいきんはん)」が起源と言われている。
2.日本のチャーハンは明治維新から
チャーハンは幕末、明治維新のころにやってきた横浜中華街の中国人からひろまった。揚子江の下流、揚州の「揚州炒飯」が日本のチャーハンの原型。
3.中央アジアから西はピラフ
チャーハンと似ているピラフ。起源は中央アジアと言われている。イスラム世界の発展とともに、ピラフは西アジア、ヨーロッパ、世界へと広がった。
4.東南アジアのチャーハンの特徴は魚醤(ぎょしょう)
稲作には豊富な水が必要。米と魚は不可分のもの。東南アジアのチャーハンの味が日本人にも親しみやすいのは魚醤(魚の発酵食品)を使っているため。
5.新日本チャーハンのカギは魚と発酵食品
「卵でパラパラのチャーハン」を目指すのではなく、魚と発酵食品を使った日本発の新しいチャーハンの開発を目指すべきである。
●「米」はどこから来たのか。諸説あれどもやはり中国
チャーハンと言えば米。米と言えばアジアの主食です。日本、韓国、台湾、フィリピンなど東南アジア諸国の主食は米です。
中国やインドもお米です。と言いたいところですが、中国は麺、インドはナンなど小麦を主食とする地域もあります。
中央アジア、西アジアも米は食べていますがパンなどの小麦の方が多いようです。イタリアやスペインでもリゾットやパエリアなどで米を食べています。主食とはいかなくても米は世界中で食べられています。
米を食べる文化、すなわち稲作の起源は中国と言われています。インド・アッサム、中国・雲南省などが発祥という説もありますが、農学研究者の佐藤洋一郎さんの書籍には以下のように書かれています。
世界最古の稲作遺跡群は浙江省一帯と湖南省一帯にある。浙江省の余姚(よよう)市には河姆渡(かぼと)遺跡をはじめとして七〇〇〇年をさかのぼる遺跡が複数あって、考古学的な研究も進んでいる。とくに、河姆渡遺跡は一九七三年の発見以来、最古の稲作遺跡として常に注目を集めてきた遺跡である。
(佐藤洋一郎 『稲と米の民族誌 アジアの稲作景観を歩く』NHK出版 2016年 p244)
現状では稲作を確実に行っていたという証拠があるのは、この7000年前の河姆渡遺跡群が最古のようです。米を食べる文化はここからはじまったと言っていいと思います。ここから世界に広がり、さまざまな米の料理を生み出してきました。チャーハンもその一つですね。
●チャーハンの祖国はチャーハンに冷たい?
チャーハンの祖国も米と同様に中国です。中国が生んだ中華料理は世界を股にかける料理の一大カテゴリーです。中華料理と一口に言ってもいろいろとあり、大きくは北京料理、四川料理、上海料理、広東料理などの4つに区分されます。
チャーハンは上海にも近い揚州で生まれたとされています。揚州は中国でも特に食文化の華やかな地です。この地で生まれたのが「揚州炒飯」です。現在のチャーハンの基本形と言えます。
2007年の雑誌『サライ』にこのような記事があります。
隋(581~619)の時代に現在の北京地方まで運河が開かれ、揚州は江南の物資を北方へ運ぶ要衝として栄えた。その海運業を支えた船乗りたちが飢えを凌ぎ手頃に食べられるものをと作られたのが、卵と飯を一緒に炒めた料理だった。隋の謝諷(しゃふう)が著した料理書『食経(しょくけい)』には「砕金飯(さいきんはん)」と記されている。これは“金のかけらのような飯”という意味で、卵炒飯の原形と考えられている。
国際的な中国料理研究家で、東京・三田の『華都飯店(シャトーハンテン)』を経営する馬遅伯昌(まちはくしょう)さん(88歳)は話す。
「私が聞いた逸話ではこうです。清の乾隆帝(けんりゅうてい)(1711~99)が南方の巡察に出向いたときに、揚州の農村で食事を所望。しかし残りご飯しかなく、これを卵と炒めて差し出した。その後、北京の宮廷に戻った乾隆帝がこの炒飯を懐かしがり、料理人に作らせたということです。もちろん料理人が作った炒飯は卵だけではなく、肉や魚などの具材を入れたものだとおもいますね」
(『サライ 2月1日号 Vol.19 No.3』2007年 p98)
隋の船乗りの話や乾隆帝の話からすると、中国でのチャーハンは「簡素な料理」という側面が強いようです。つまり正式な中華料理として評価されていないのだと思います。
中国料理には肉や魚、野菜について技巧をこらした料理がたくさんあります。しかし料理書のレシピをみても多彩な食材や技術を使っているチャーハンは少ないようです。家庭料理やまかない飯として見られているのではないでしょうか。
チャーハンの祖国ではあるものの、あつあつのチャーハンでも、ほんの少し冷たいところが感じられます。
●米をつくらない中央アジアでなぜ米料理ピラフなのか
中国の影響が強かった国ぐにではそれぞれの国のチャーハンを見かけます。しかし中央アジア、西アジア、ヨーロッパではチャーハンは見当たらず、ピラフがメインです。
ピラフはチャーハンに似ていますが、つくり方は違います。ご飯と具材を一緒に炊き込むため、後から炒める工程がありません。
ピラフという名称の語源も定かではありません。中央アジアのウズベキスタンでは「プロフ」、イランでは「ポロ」、トルコでは「ピラウ」と呼ばれ、その他の国でもいろいろな呼ばれ方をされています。
ピラフ発祥の地についても中央アジア、西アジアとも言われますが詳しいことはわかっていません。インドにもピラフはありますが、ビリヤニというインド独自のものもあります。こちらもまた作り方には、さまざまな理論と方法があります。
スペイン料理のパエリアはピラフの面影があります。しかしイタリア料理のリゾットはピラフの仲間かもしれませんが、その姿は粥(かゆ)を想起させます。
厳密に考えれば「ピラフ」という名前ではひとくくりにできず、どれもが違った米料理と言えるかもしれません。
中央アジア、西アジア、ヨーロッパではパンを始めとした麦を食べることが多い国ぐにです。なぜ米をつくらない国でピラフのような米料理がここまで食べられるようになったのでしょうか。
●イスラム世界の発展とピラフの広がり
ピラフについてはアレキサンダー大王の東征がピラフをさまざまな地域に広めたという伝説もあります。しかし、伝説以上ではないようです。日本で言えば弘法大師伝説のようなものでしょうか。
ピラフについての最古の記述は、イスラム世界の最高の知識人と言われるアッバース朝時代の学者イブン・スィーナーの著書にあります。アッバース朝は西暦750年から1258年まで続いたイスラム王朝です。中央アジア、西アジアだけでなく北アフリカ、イベリア半島までを領有していました。
このアッバース朝時代はイスラムの繁栄の時代でした。広大な領土のなかをイスラム商人たちが、シルクロードやインド洋から中国までの海のシルクロードを使って交易をしていました。香辛料や陶磁器、絹織物、象牙などの交易はイスラム諸国に繁栄をもたらせました。
インドネシア、マレーシアにイスラム教徒が多いのはこの時代にイスラム教が入ってきたことによります。15世紀にはイスラム教国であるマラッカ王国(1402年 – 1511年)がマレーシア半島に誕生しています。
マラッカのイスラム商人たちはジャワ島で米を買い付け、同時にイスラム教も伝えていました。これによってイスラム教が東南アジアに広がっていきました。このイスラム商人たちが買い付けた米がピラフとなって、その味をイスラム世界へ、ヨーロッパへと広げたと推測できます。
アッバース朝と言えば、唐王朝時代の中国と戦争になったこともあります。751年の「タラス河畔の戦い」です。現在の中央アジア、キルギスのタラス地方です。
この戦争によってアッバース朝は唐の軍勢を撃退し、大量の捕虜を得ました。その中に、当時中国の独自技術であった製紙法を知る人物がいたため、紙がイスラム世界に伝わりました。それはやがてヨーロッパに伝わり、紙は広く西洋でも使われるようになりました。
「伝わったのは紙だけだったのか」。「もしかするとチャーハンもその時にイスラム文化圏に伝わり、それがピラフになったのではないか」。私の妄想です。しかしピラフの発祥が中央アジアということであれば「ないことはない」と思っています。
新しい料理の広がりは、日本のチャーハンのはじまり同様に、大きな人の移動、その人が運んできた食文化の広がりと密接な影響があると考えます。明治維新、タレス河畔の戦いなど劇的な変化は食文化にも大きな変化を生むのだと思います。
中央アジアのピラフもイスラム世界の大いなる発展とともに西アジアを経てヨーロッパ、そして世界各地に広がったのだと思います。
●東南アジアのチャーハン、共通するのは魚醤(ぎょしょう)
突然ですが世界で米の消費量が一番多い国はどこでしょうか? クイズ王でもなければわかりませんね。
答えはバングラデシュです。その消費量は一日で470g。お茶わん一杯分のご飯になる米(生米)を68gと換算して約7杯分です。
では2位はどこでしょうか?実は2位は二つあってラオスとカンボジアなのです。一日436gも食べます。その次の4位にはベトナムがランクインします。こちらは396gです。その他のアジア各国も一日の米の消費量ランキングでは上位に入っています。
ちなみに日本は164gで32位です。ピークだった1962年は324gでしたからほぼ半分です。米の消費に関しては、そろそろアジアから除名されてしまうかもしれませんね。
日本の米はジャポニカ米という種類です。もちもちした食感が特徴です。しかし世界全体で生産量が多いのは細長い形のインディカ米です。パラパラという食感です。ここに日本人のチャーハンパラパラ願望が関係していると思います。ジャポニカ米ではなかなかパラパラにはできません。
いずれにしろ東南アジアはたくさんの米を生産し、消費する「米を愛する国ぐに」ということです。
ということで、東南アジアのチャーハンを食べてみました。それぞれの国に行くことはできませんので、東京にあるタイ、ベトナム、ミャンマー、カンボジア、インドネシアの料理専門店に行ってみました。
この国のチャーハンはこれという決まりがあるわけではありません。その店の独自レシピもあるので、ここでは印象ということでご覧ください。
タイのチャーハンの特徴はやはり辛味です。タイの人は辛さや酸っぱさや甘みがミックスした料理を好むと言われています。チャーハンも例にもれず、いろいろな味がミックスされた上に、パクチーもトッピング。タイらしいおいしさです。
ベトナムのチャーハンは日本のチャーハンに近く、食べやすいチャーハンです。ベトナムは中国とも国境を接しています。歴史的な付き合いも長く深く、日本と同じように中国のチャーハンが伝わってきたのではないかと推測します。
ミャンマーは多民族の国です。料理もその民族それぞれのものがあります。ミャンマー料理店で食べたのはシャン風納豆チャーハン。おいしいチャーハンでした。こちらも中国のチャーハンの影響が大きいように思われます。食べていませんが高菜チャーハンもありました。納豆チャーハン、高菜チャーハンは日本にもありますね。
カンボジアのチャーハンはレモングラス入りです。レモングラスはハーブの一種でレモンのような香りがします。ちょっと濃い目の味わいです。これもおいしい。決め手はカンボジアの魚醤(ぎょしょう)のようです。
インドネシアのチャーハンはナシゴレン。えびやフライドオニオンがメインです。フライドエッグが乗っていました。イスラム教徒が多い国ですから肉を使うことについては気をつかっているのかもしれません。
東南アジアの国ぐにのチャーハンは日本のチャーハンと比べた時に独特のうま味があります。このうま味はどこから来るものなのでしょうか。
●魚の国のチャーハン。米あるところに魚あり
稲を育てるためには大量の水が必要となります。田のまわりには豊富な水があります。水中の微生物たちが陸上からもたらされる栄養分で生育されます。それを狙って魚が寄ってきます。その魚は食卓にものぼります。水の豊富な地域は、米をつくりやすいのと同時に魚との結びつきが強くなります。
前述の米や稲作に詳しい農学研究者の佐藤洋一郎さんは、著書のなかで「米と魚の同所性」と言っています。「米あることころに魚あり」ということです。
東南アジアのような魚が豊富に獲れるところでは塩を使って魚醤にすることで天の恵みである魚を余すことなく利用しています。
東南アジア料理の味付けには魚醤多くが使われています。魚醤は発酵食品です。
タイならナンプラー、ベトナムならニョクマム、ミャンマーだとンガピャーイェー、カンボジアならトゥック・トレイ、インドネシアだとケチャップ・イカンという名前がそれぞれに付いています。日本でも秋田の「しょっつる」や能登の「いしる」などがおなじみです。
魚醤だけでなくミャンマーのチャーハンで使われている納豆や高菜も発酵食品です。日本人にもなじみやすく、おいしさを感ずるのはここだと思います。
つまり東南アジアのチャーハンのおいしさは魚醤あるいは発酵食品です。ピラフにはあまり見られない魚の力を使っているという点です。
●日本のチャーハンについて考える。ジャポニカ米と魚と発酵食品
日本の米は炊きあがるとモチモチとしています。東南アジアの米はジャバニカ米という短粒種ですがそれほどモチモチしていません。インディカ米はサラリとしていてチャーハンもパラパラになります。このパラパラ感をジャポニカ米で求めるのは、そもそも難しい話ではないでしょうか。
東南アジアのチャーハン食べ歩きでわかったことは魚醤という魚の発酵食品の力です。
日本のチャーハンを高めていくなら、時間をさかのぼって「揚州炒飯」のようなパラパラを求めるのではなく、「魚と発酵食品」を使って新しい日本のチャーハンをつくるべきではないでしょうか。
日本のジャポニカ米。そこに魚醤、魚、発酵食品で「新日本チャーハン」をつくっていくべきではないでしょうか。
主な日本の発酵食品は魚介では、かつお節・魚醤・塩辛・くさや・なれずし、豆では、納豆・しょうゆ・みそ、野菜・穀物では、漬け物・甘酒・酢・酒粕などがあります。このなかのどれかを使って組み合わせていくことで日本のチャーハンが進化すると確信しています。
●やってみた。新日本チャーハン。かつお節チャーハン
「言ってみただけ」ではおさまりがつきませんね。シロウトですがチャーハンならつくれます。
日本伝統の発酵食品かつお節をメインにしました。しょうゆと沢庵、魚醤として秋田のしょっつる。さらに魚である塩鮭、卵にネギを使ってつくってみました。
できあがりは写真のとおりです。「ウマイ!」。…こうでも言わないと引っ込みがつきませんね。
シロウトですが、あえて言うと上にのせたかつお節よりも炒めたかつお節はいい味が出ています。塩鮭は当然ながらごはんにあいます。沢庵はイマイチ。秋田のしょっつるは隠し味程度で、もう少し使ってもよかったかもしれません。でも、この食材ならつくり方を間違えなければだいたいおいしくできるはずですね。
もっと劇的な味を求めるなら魚介系の発酵食品を使う必要があるのかもしれません。イカの塩辛、八丈島のクサヤ、琵琶湖の鮒ずしなどのなれずしもあります。クサヤ、なれずしは刺激的な食材です。でも魚介系の発酵食品にはなにか新しいものを感じます。新しい日本のチャーハンができるのではないでしょうか。
「これが日本のチャーハンの夜明けぜよ」。かつお節に敬意を表して坂本龍馬風の土佐弁でシメです。
あらためて最後にまとめです
1.米とチャーハンは中国が起源
稲作は約7000年前の揚子江下流からはじまった。チャーハンは隋(581~619)の時代の「碎金飯(さいきんはん)」が起源と言われている。
2.日本のチャーハンは明治維新から
チャーハンは幕末、明治維新のころにやってきた横浜中華街の中国人からひろまった。揚子江の下流、揚州の「揚州炒飯」が日本のチャーハンの原型。
3.中央アジアから西はピラフ
ピラフの起源は中央アジアと言われている。イスラム世界の発展とともに、ピラフは西アジア、ヨーロッパ、世界へと広がった。
4.東南アジアのチャーハンの特徴は魚醤(ぎょしょう)
稲作には豊富な水が必要。米と魚は不可分のもの。東南アジアのチャーハンが日本人にも親しみやすい味わいなのは魚醤(魚の発酵食品)を使っているため。
5.新日本チャーハンのカギは魚と発酵食品
卵でパラパラのチャーハンを目指すのではなく、魚と発酵食品を使った日本発の新しいチャーハンの開発を目指すべきである。
参考文献
佐藤洋一郎『知ろう 食べよう 世界の米』岩波ジュニア新書 2012年
佐藤洋一郎編『食の文化フォーラム26 米と魚』ドメス出版 2008年
譚璐美『中華料理四千年』文春新書 2004年
『サライ 2月1日号Vol.19』小学館 2007年
西川武臣/伊藤泉美『開国日本と横浜中華街』大修館書店 2002年
田中静一『一衣帯水-中国料理伝来史』柴田書店 1987年
藏中進『『倭名類聚抄』所引『楊氏漢語抄』』東洋研究第145号大東文化大学東洋研究所 2002年
荻野恭子『世界の米料理 世界20カ国に受け継がれる、伝統的な家庭料理』誠文堂新光社 2015年
私市正年監『イスラム世界-世界に15億人!イスラムのすべてを知るための一冊』日東書院本社 2015年
石毛直道編『論集東アジアの食事文化』平凡社 1985年
石毛直道監『人類の食文化 (講座 食の文化)』味の素文化センター 1998年
石毛直道/ケネス・ラドル『魚醤とナレズシの研究』岩波書店 1990年
土屋敦『男のチャーハン道』日本経済新聞出版 2018年
*米の消費量の出典:FAO〈国際連合食糧農業機関〉、農林水産省HP
ビリヤニ、タイチャーハン、カンボジアチャーハン